土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域とは? ~不動産売買への影響~
近年、各地で地震や集中豪雨などによる土砂災害被害が増加しており、行政が危険箇所の指定を進めています。
「土砂災害警戒区域」や「土砂災害特別警戒区域」に指定されると、不動産の売却価格が低下する、建物の建築に制限が設けられるなど、様々な影響を受けることがあります。
そのため、不動産売買の際には、対象不動産が土砂災害(特別)警戒区域内にあるのかどうかを確認する必要があります。
.jpg)
目次
- ○ 土砂災害とは?
- ○ 土砂災害防止法とは?
- ○ 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
- ○ 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
- ・建築に対する制限
- ・特定の開発行為に対する制限
- ・建築物の移転勧告と支援制度
- ○ 土砂災害警戒区域が不動産売買に与える影響
- ・価格下落の可能性
- ・住宅ローン審査への影響
- ・売買時の告知義務と法的責任
- ○ まとめ
土砂災害とは?
「土砂災害」とは、大雨や地震、火山活動などの自然現象を引き金に、山やがけが崩れ落ち、土砂が流れてくることによって人家や田畑、道路などが埋まり、様々な被害を与える自然災害です。
代表的な災害には、以下の3つがあります。
• 土石流:山や谷の土石が雨水と一体となって、一気に流れ出てくる現象
• 地すべり:地中の水分を含んだ地盤が、広範囲にわたって滑り落ちていく現象
• がけ崩れ:急な斜面が突然崩落し、大量の土砂が一気に崩れ落ちてくる現象
これらの災害は突発的に発生しやすく、人的被害や財産への損害が甚大になるため、事前の対策が大切です。
土砂災害防止法とは?
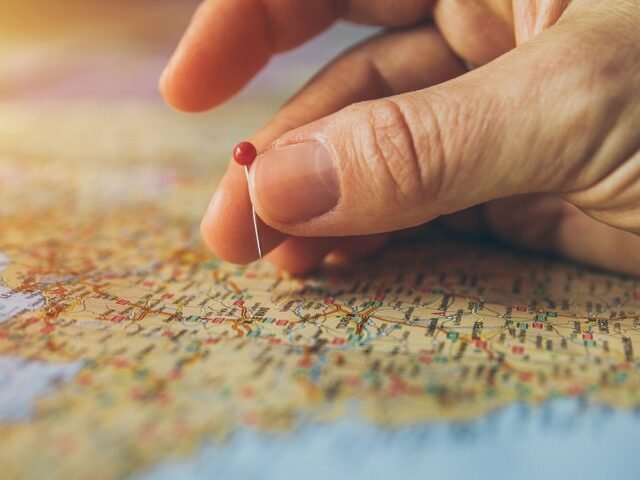
土砂災害に対する国の法的政策として、2001年(平成13年)に施行されたのが「土砂災害防止法(正式名:土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)」です。
従来は、「砂防法」「地すべり等防止法」「急傾斜地崩壊防止法」の3法(通称:砂防三法)によって、土石流、地すべり、がけ崩れの3つの土砂災害の発生を防止するために、砂防工事や地すべり防止工事などのハード対策が行われていました。
しかし、広範囲にわたる危険地域への対策工事を進めるには、膨大な時間と費用がかかるため、土砂災害防止法では「危険の周知」「避難体制の整備」「住宅等の建築への制限」「既存住宅の移転促進」など、工事によらないソフト対策が推進されるようになりました。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
土砂災害の発生リスクがあると見込まれる場所において、各都道府県が基礎調査を実施し、住民の命や安全に危害が及ぶ危険性があると判断された区域は、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」に指定されます。
区域については、5年ごとに再度調査が行われ見直されます。
イエローゾーンに指定された区域では、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
• 住民への危険箇所の周知の徹底
(市町村長は、土砂災害に関する情報伝達、避難地に必要な情報を住民に周知させるために、ハザードマップ等を配布し、その他必要な措置を講じる)
• 避難計画や避難経路の整備
(高齢者や障害者など、自力避難が困難な災害時要援護者が利用する施設が区域内にある場合、円滑な警戒避難を実施するために、土砂災害に関する情報等の伝達方法を定める)
イエローゾーンでは、原則として建築そのものに対する直接的な制限は設けられていません。
一方で、自然災害リスクのある地域であることが明示されているため、不動産取引において、宅建業者は対象物件が警戒区域内である旨を説明する義務があります。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土砂災害警戒区域の中でも、特に危険性が高く、土砂災害が発生した場合、建物倒壊や人命への重大な被害が及ぶと予想される地域は、「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」に指定されます。
この区域に指定されると、建築物の構造や開発行為に対して様々な制限が課されます。
イエローゾーン同様、宅建業者は、対象物件が土砂災害特別警戒区域にあることを説明する義務があります。
また、特別の開発行為において、都道府県知事の許可を受けた後でなければ、当該宅地の広告や売買契約締結が行えず、当該宅地または建物の売買にあたり、特定の開発の許可についての重要事項説明を行うことが義務づけられています。
建築に対する制限

レッドゾーン内で住宅を新築・改築・増築する場合、以下のような耐災害構造を備えることが求められます。
• 想定される土石流の高さ以下にある部分はRC(鉄筋コンクリート)造
• 土圧や衝撃に耐える強固な耐力壁の設置
• 基礎と壁を一体化する構造
これらの要件を満たさなければ、建築確認が下りないため、設計段階から専門家との入念な調整が必要です。
特定の開発行為に対する制限

次のような施設を建設するために行う開発行為は、都道府県知事の許可が必要になります。
• 住宅地分譲
• 高齢者施設・福祉施設
• 教育機関(幼稚園・保育園など)
• 医療機関(診療所・病院など)
特に福祉・医療関連施設は要配慮者の利用が多いため、災害時のリスク管理が厳しく問われます。
建築物の移転勧告と支援制度

レッドゾーンに指定されたエリアにおいて、土砂災害が発生した場合に、住民の生命等に著しい危害が生じる恐れのある建築物の所有者や居住者に対して、自治体が安全な区域への「移転勧告」を出すケースもあります。
その際は、以下のような支援措置が適用されることがあります。
• がけ地近接等危険住宅移転事業(移転費用や代替家屋建設費用への一部補助)
・住宅金融支援機構の融資(地すべり等関連住宅融資)
ただし、補助制度は自治体ごとに内容が異なるため、役所へ確認しておくことをおすすめします。
土砂災害警戒区域が不動産売買に与える影響
土砂災害(特別)警戒区域内にある不動産の売買は、以下の影響を受ける恐れがあります。
価格下落の可能性
災害リスクが可視化された地域では、買い手の需要が減少し、価格が下落することがあります。
特にレッドゾーンに指定された区域は、建築の制限や災害リスクの大きさから、一般的に評価額が低く見積もられる傾向があります。
また、購入希望者にとってもリスクが高いため、成約までに時間がかかってしまうこともあります。
住宅ローン審査への影響
区域の指定により、金融機関が融資判断を厳格化するケースもあります。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)では、区域内に新築住宅を建設・購入する場合、「フラット35S」、「フラット35維持保全型」の住宅ローンを利用できません。
災害の危険性が極めて高い区域の人口が、これ以上増加するのを防止するためです。
売買時の告知義務と法的責任
不動産取引では、対象物件の所在地が、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や特別警戒区域(レッドゾーン)に該当する場合、その旨を重要事項説明書で明確に説明することが、宅建業法第35条により義務付けられています。
万が一、説明義務違反があった場合、売主や仲介業者は契約解除や損害賠償請求をされるおそれがあります。
そのため、売主自身も、事前に自治体のハザードマップや公式情報などで、区域指定の有無を確認し、信頼性の高い情報を提供することが不可欠です。
まとめ

土砂災害警戒区域および特別警戒区域に指定された不動産を売買する場合は、通常の取引以上に情報の把握と対応が重要です。
建築制限や価格への影響、住宅ローンの条件など、様々な要素を踏まえて慎重に検討することが求められます。
不動産取引に不安がある方は、地域に精通した専門の宅建業者や、行政機関と連携をとり、安全で納得のいく取引を目指しましょう。
-------------------------------------------------
この記事を読む皆様が納得のいく不動産売却ができるように切に願っております。
福岡市東区・糟屋郡の不動産売却、不動産購入
不動産関係で何かお困りのことがあれば、小さなことでも是非弊社までご連絡ください!
↓↓↓無料査定は下記リンクをクリック!↓↓↓

